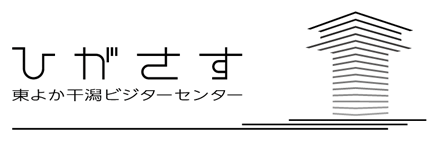東よか干潟について
2015年、国際的に重要な湿地としてラムサール条約湿地に登録


東よか干潟は、佐賀市南部の有明海湾奥部に広がる泥の干潟です。
有明海の干満差は最大約6mと日本最大で、干潮時は見渡す限りの広大な干潟が姿を現します。
渡り鳥であるシギ・チドリ類の渡来数は日本一を誇り、絶滅危惧種を含む水鳥類の国内有数の中継地・越冬地となっています。また、干潟には、ムツゴロウやワラスボ、シオマネキなど、泥干潟特有のユニークな生きものが多く生息しています。
[登録番号]2234
[登録年月日]2015年5月28日
[面積]218 ha
[湿地のタイプ]G:潮間帯の泥質、砂質、塩性干潟
[保護の制度]国指定鳥獣保護区特別保護地区
[国際登録基準]2、4、6
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)
ラムサール条約は1971年2月2日にイランのラムサールという都市で開催された国際会議で採択された、湿地に関する条約です。正式名称は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」といいますが、採択の地にちなみ、一般に「ラムサール条約」と呼ばれています。
2021年2月末現在、世界で171ヶ国が加入しています(日本は、1980年に加入)。
ラムサール条約では、沼沢地、湿原、泥炭地または陸水域、および水深が6メートルを超えない海域などを、湿地と定議しています。その中には、湿原、湖沼、ダム湖、河川、ため池、湧水地、水田、遊水地、地下水系、塩性湿地、マングローブ林、干潟、藻場、サンゴ礁などが含まれます。湿地分類の詳細は、こちらを参照してください。https://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/Wetland_Type.html
国際的に重要な湿地の選定基準
基準1: 特定の生物地理区内で、代表的、希少または固有の湿地タイプを含む湿地。
基準2:絶滅のおそれのある種や群集を支えている湿地。
基準3:特定の生物地理区における生物多様性の維持に重要な動植物を支えている湿地。
基準4:動植物のライフサイクルの重要な段階を支えている湿地。または悪条件の期間中に動植物の避難場所となる湿地。
基準5:定期的に2万羽以上の水鳥を支えている湿地。
基準6:水鳥の1種または1亜種の個体群の個体数の1%以上を定期的に支えている湿地。
基準7: 固有な魚介類の亜種、種、科、魚介類の生活史の諸段階、種間相互作用、湿地の価値を代表するような個体群の相当な割合を支えており、それによって世界の生物多様性に貢献している湿地。
基準8:魚介類の食物源、産卵場、稚魚の生育場として重要な湿地。あるいは湿地内外の漁業資源の重要な回遊経路となっている湿地。
基準9:鳥類以外の湿地に依存する動物の種または亜種の個体群の個体数の1%以上を定期的に支えている湿地。
注)魚介類:魚、エビ、カニ、貝類
干潟に渡来する野鳥たち
 東よか干潟の野鳥(2月)
東よか干潟の野鳥(2月) ハマシギ
ハマシギ
(8月〜5月)
 ダイシャクシギ
ダイシャクシギ
(8月〜5月)
 クロツラヘラサギ
クロツラヘラサギ
(11月〜4月)
 ズグロカモメ
ズグロカモメ
(11月〜5月)
 ツクシガモ
ツクシガモ
(12月〜4月)
干潟の生きものたち
 ムツゴロウ
ムツゴロウ
(4月〜10月)
 トビハゼ
トビハゼ
(4月〜10月)
 シオマネキ
シオマネキ
(4月〜10月)
 シチメンソウ
シチメンソウ
(紅葉10月下旬〜11月上旬)
シチメンソウの状況と環境保全協力金(佐賀市)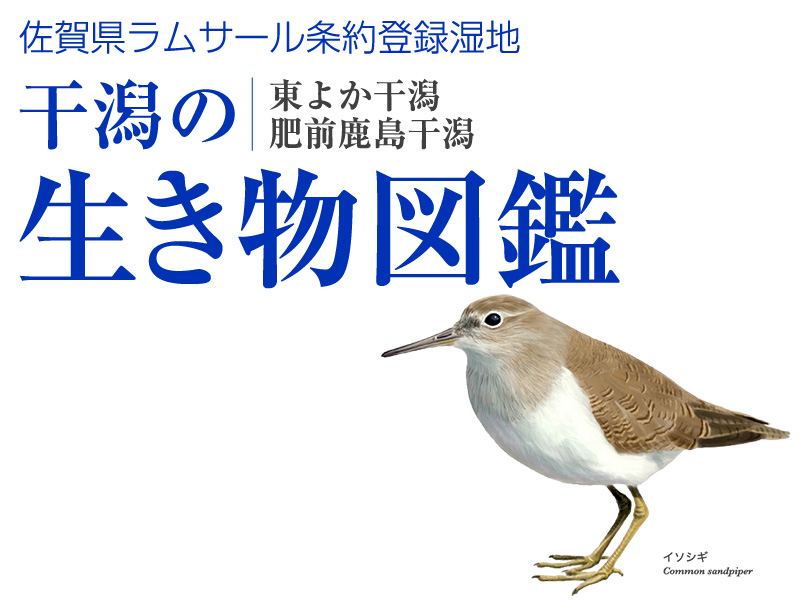 干潟の生き物図鑑
干潟の生き物図鑑
干潟の生き物について詳しく知りたいかたはこちら
干潟のワイズユース(賢明な利用)
 のり養殖の風景
のり養殖の風景
販売枚数・販売額ともに日本一を誇る「佐賀海苔」
 タカッポ漁
タカッポ漁
昔から続くムツゴロウの伝統漁法「タカッポ漁」
 シギの恩返し米
シギの恩返し米
自然との共生を目指すシギからの感謝の贈り物
シギの恩返し米ホームページ
フォトギャラリー
東よか干潟のフォトギャラリーです。